![]() トルクメニスタン共和国 Republic of Turkmenistan |アジア
トルクメニスタン共和国 Republic of Turkmenistan |アジア
遊牧民の料理とカスピ海の漁民の料理
中央アジアの南西部にあり、かつてはソ連に属していたトルクメニスタン。国名は「トルクメン人の国」という意味で、国土の80%を占めるというカラクム砂漠に太古の昔から暮らす、トルコ系遊牧民の国です。
独立後、近年は独裁国家として知られるようにもなりましたが、天然資源が豊富であり、また企業や大学を通して日本とも交流の深い親日国でもあります。

↑ピシュメ
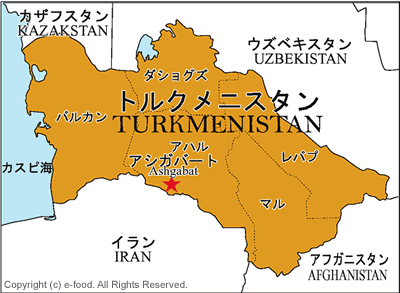
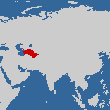
主な料理は、串焼き肉のシャシリク (ケバブ)や、肉を詰めた小麦粉のゆで団子のマンティ、肉と野菜のスープのショルパ、とうがらしやにんにく、サフラン、ミントの入ったラクダの肉のスープGaynatma、同じレシピの羊肉バージョンのDograma、黄色いカブを添えた羊肉や雉肉のプロフ(ピラフ)、羊の脂で羊肉を揚げたKa’urmaなど。
また、細長いライ麦パンのチャパッド、揚げパンのピシュメ(上写真)や、揚げたライ麦パンのエクメクなどもあります。
トルクメニスタン料理の地方色
トルクメニスタンには、遊牧民のほかにも、アムダリヤ川などの流域に農民が、カスピ海沿岸に漁民が暮らしており、それぞれに習慣の違いがあります。
東部の砂漠地方は、典型的な中央アジアの食文化圏。肉が好まれ、羊やラクダ、山羊、鶉、雉といった動物が食用とされて、揚げたり、串焼きにしたり、オーブンで焼かれて調理されます。
また東部では、肉を保存する変わった方法が用いられています。それは、塩ととうがらしをすり込んだ羊や山羊の胃袋に肉を入れて縛り、熱した砂を掘って1日置くというもの。肉は、夕方の涼しい風が吹く頃に掘り起こされ、棒に吊るして乾燥させます。こうした手順を何度か繰り返すことで、肉に独特の風味がつき、長期間保存できるのだといいます。
一方、カスピ海沿岸では、肉よりも、チョウザメやボラ、なまずといった魚の料理の方がポピュラーです。これらはご飯を添え、レーズン、アプリコット、胡麻などを使って時には甘酸っぱく、時にはピリッと味に調理され、中には、チョウザメのシシカバブといった食べ方も。
トルクメニスタンでは、東部の砂漠の人が、カスピ海沿岸の人からチョウザメの料理をごちそうになると、「ラムのような味がする」といって主人を喜ばせ、反対に、カスピ海沿岸の人が砂漠の人にラム料理をごちそうになると、「まさにチョウザメのような味だ」と賞賛するくらいなのだといいます。
トルクメニスタンの飲み物
飲み物は緑茶が定番。脂っこい肉料理を食べた後に胃をすっきりさせる効果があります。
また砂漠地方では、ヨーグルトドリンクのアイランや、新鮮なラクダの乳を日陰に2日ほど置き、ときどきかき混ぜて脂肪をすくいながら作るチャル(Chal)という少し酸味のある乳飲料も好まれています。
トルクメニスタン料理の写真
シャシリク
トルクメニスタン料理のレシピ





