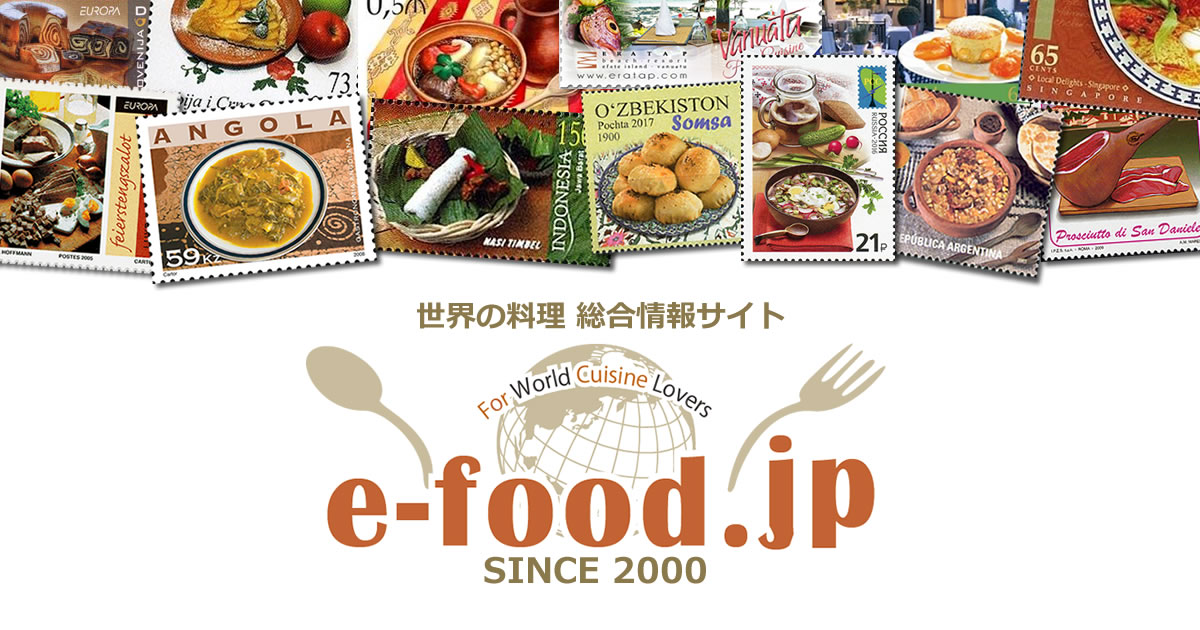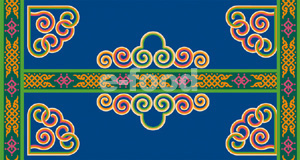チンギス・ハーンを輩出した遊牧民の国

↑ボーズ
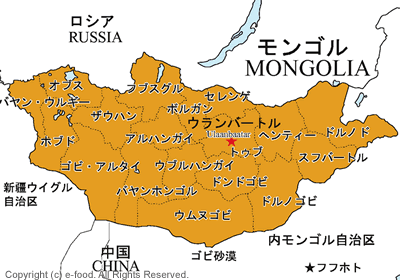

モンゴルは、現在のモンゴル国にあたるゴビ砂漠以北の地域と、現在は中国の領土となっている南部の内モンゴル自治区に大きく分かれます。もともとは同じ民族でも、地理的な条件や、ロシア、または中国の影響があるかないかで食文化も少し違い、内モンゴル共和国は漢民族の影響が年々高まっているともいわれます。以下に両地域の特色についてまとめてみましょう。
モンゴル国の料理
モンゴル国の国土の5分の4を占めるモンゴル高原は、寒冷と乾燥の地で農業に向かず、そのため人々は古くから、家畜とともに草原を移動する遊牧民を生業としてきました。モンゴル高原で放牧されるのは、羊、山羊、馬、牛、ラクダで、その中でも羊は、モンゴル遊牧民の食生活になくてはならない家畜です。
モンゴルの高原では、夏には「白い食べもの」 を、冬には「赤い食べもの」を多く食べるといいます。白い食べものとは乳製品、赤い食べものとは肉のこと。乳製品には、バター風味の生クリームのようなウルム(パンに乗せて食べたりする)や、ウルムを発酵して加工したタラグ(ヨーグルト)、同じくウルムから作るビャスラグやエーズギーといったチーズ、ウルムと小麦粉を熱してシチューのルー状にしたハイルマック、ロシア風のバターのマースロなどがあります。
一方、肉を使った料理には、まず、シュース(チャンスンマハ)という羊肉の塩ゆで。ホルホグという石焼きした羊肉(山羊の場合はボードグという)。そして、ボーズというミンチした羊肉の入った蒸した肉まん、バンシという水餃子、ホーショールという焼いたピロシキのような軽食、ツォイワンというモンゴル風の焼きうどん、ゴリルタイ・シュルというモンゴル風の肉入り汁うどんなどがあります。モンゴルの料理は香辛料を使わず、塩とねぎなど薬味だけのシンプルな味付けが一般的。その代わり、塩は肉の旨みを引き出す岩塩が用いられます。
ただし、首都ウランバートルでは、ケチャップやマヨネーズなど外来の調味料が使用され、外国の料理も食べられているようです。
飲み物はお茶、お酒はアルヒという乳の蒸留酒や、アイラグ(馬乳酒。本来は乳酒の意味。カザフスタンなど中央アジアでは同じものをクミス、またはクムスという)。アルヒやアイラグといった乳酒は、モンゴルの草原の自然環境が生み出した乳糖発酵性酵母のなせるわざで、世界で唯一の動物性の酒といわれています。
ところで、かつてモンゴル草原の民は野菜をほとんど食べなかったそうです。モンゴル人のいう「草は(食用にする)羊が食べているからいいんだ」というのは冗談にせよ、馬乳乳にはビタミンCをはじめとする栄養素が豊富に含まれ、また食物繊維の摂取に代わる機能を果たしているともいわれています。馬乳酒を1日10リットルを飲む成人男子が、それ以外の食べ物を摂らないことも珍しくないのだとか。馬乳酒は実際、血圧を下げたり、免疫力を活性化させる効果が認められていて、まさにプロバイオティクスの先駆け的な存在といえそうです。
内モンゴル自治区の料理
中国側の内モンゴル自治区は、大まかにはモンゴル国よりも温暖かつ湿潤であり、食材も豊富であり、農耕が盛ん。人口密度はモンゴル国の12倍以上で、草原に暮らす遊牧民の国とはいえません。内モンゴル自治区のおよそ2500万の人口のうち、モンゴル民族は400万人以下で、漢人が大多数を占めているというデータもあります。
というわけで、内モンゴル自治区の料理は、中国の影響が強くうかがえ、遊牧民というよりは農耕民の料理が主流。小麦粉を使った「シェルビン」(モンゴル国の「ホーショール」に類似)、「ボーズ」、「バンシ」や、モンゴル・アム(炒米)という蕎麦の一種が内モンゴル全域で食べられているほか、3つに大きく分けられた地域によって特徴があります。
草原モンゴル料理(陰山山脈から大興安嶺より北部の地域)
モンゴル王侯貴族に雇われてきた漢人の料理によって形成された羊料理。チンギス・ハーンが好んだ「羊の腿焼き」、フビライ・ハーンにゆかりのある「羊肉のしゃぶしゃぶ」、今も祝宴に欠かせない「羊の丸焼き」のほか、熊の手のひら、らくだの足の裏、鹿の筋などの料理もあります。
東部内モンゴル料理
内モンゴルの中でもモンゴル民族の人口が多い地域であり、山東省や河北省の漢人の文化とミックスした料理が特徴的。代表的な料理は「爆ネギ羊肉」。
西部内モンゴル料理
内モンゴルの首都フフホトのある、漢人の多い地域。代表的な料理は「シュウマイ」 、「ユウメン」(はったい粉の一種をこねてゆでて食べる料理)。
モンゴル料理の写真

チャンスンマハ
モンゴル料理のレシピ