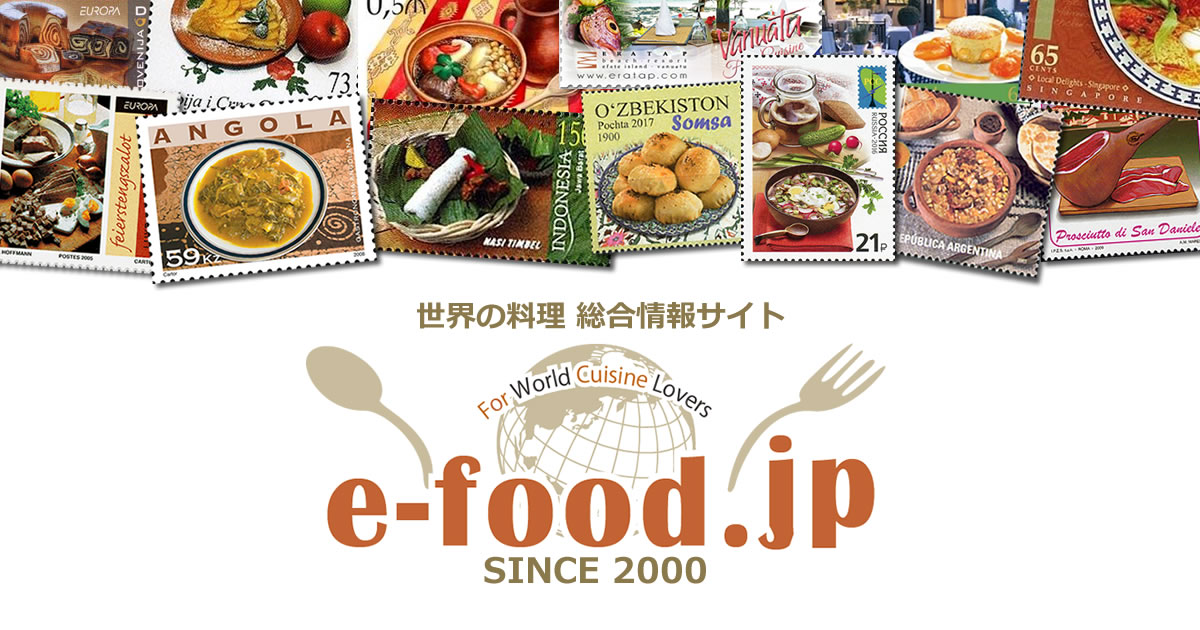四季折々の食材を使った、地方色豊かな料理
南北に長い列島を国土とし、四季折々の海の幸、山の幸に恵まれた国、日本。山に隔たれた地形と数多くの島々には、独自性を持つ風土を育み、世界的に見ても地方色の豊かさは目をみはるばかりです。
その豊富な郷土料理、そして千年の都・京都を中心に育まれた和食文化は、「和食;日本人の伝統的な食文化」として2014年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。

↑手まり寿司

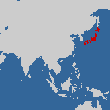
日本の地方料理について
現在、日本には47の都道府県がありますが、歴史から食文化を考察する上では、明治時代以前の藩の区分を念頭に置く必要があります。これはかつての小さな藩王国が合併してできたインドやイタリアなどにも共通する認識です。
日本の各地方ごとの料理や食文化については「日本の郷土料理食べ歩き」をご覧ください。
日本の”舶来料理”について
一方、うどんや天ぷら、寿司といった、現在、日本を代表する料理も、原型は海外からやってきたものだということも忘れてはいけません。これらは日本で独自発展して、日本ならではの料理として根付いていったのです。明治以降に到来したカレーやラーメン、またナポリタンに代表される洋食などもその部類に入ると思われます。
また、近年は首都・東京などで世界のあらゆる国の料理がレストランなどで食べられるようになりましたが、舶来の”各国料理”が持てはやされるようになったのは、今に始まったことではありませんでした。たとえば、6世紀の大和朝廷の時代には、蘇(そ)という牛乳を炊き上げて作ったチーズがシルクロードから伝わり、尊い人の間で珍重されていました。
また、鎌倉時代には、禅宗の影響で精進料理が食べられるようになり、足利末期には南蛮料理が伝わりました(これらを取り入れたのが、京都の茶懐石やおばんざいだといわれています)。
江戸時代の天文年間には長崎にポルトガル人が渡来し、また日本人の使節がポルトガルに渡って日本の食文化に影響を与えました。たとえば、天ぷら(ポルトガル語ではフィレッテ)やかき揚げ(パタニスカス・デ・バカリャウが祖先といわれる)など、油を使った料理が普及したのもこの時代です。
およそ80年後の元和年間には、ポルトガルに代わって唐の文化が入り始め、支那うどん(ラーメン)や、お好み焼きの元祖ともいえる”煎餅”が伝わりました。
明治時代に入ると、長年の肉食禁忌が解かれ、牛肉食が文明開化の象徴になりました。インドからヨーロッパに伝わったカレーが食べられるようになったのもこの頃です。横須賀の名物として有名になった「海軍カレー」も、西欧式のカレーでした。カレーと一緒に牛乳とサラダを一緒に食べるのが、当時の流儀だったようです。ラーメンもお好み焼きもカレーも、独自の発展を続け、今や日本を代表する食となりました。
一方、日本を代表するお酒といえば、日本酒(Sake)。今や世界各地にSake Barがあるほど国際的な存在です。古事記と前後して奈良朝時代に編さんされたといわれる「播磨風土記」には、すでに日本酒の製法が綴られていました。また、日本で喫茶の文化が始まったのは、遣唐使が往来した奈良・平安時代といわれています。
2024年には、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。
日本料理の写真

古代のチーズ”蘇”
日本料理のレシピ