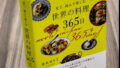世界10都市のシェフ&郷土料理が一同に集結

2024年12月7日に山形県鶴岡市で開催された「つるおかふうどフェスタ」の翌日に行われたレセプション「風土xFOOD Night」に参列させていただきました。
「食の理想郷」鶴岡市の人々の気合いと心意気
この催しは、同市が日本で初めてユネスコの食文化創造都市のネットワークとして認定されてから10周年を記念したものです。世界9都市の食文化創造都市および同市の姉妹都市からシェフが来日して鶴岡を含めた10都市のシェフが集結。そして、庄内地方の高品質で新鮮な食材を使った自慢の郷土料理を振舞うという、東京でもめったにない、食べもの好きには夢のような特別の夕べでした。
中には、西アフリカの国ベナンの食文化創造都市ボヒコンの「ボミオ」のような大変希少な料理も。1月10日に作るブードゥー教のお祝い料理が元になった、丸ごとの鶏を添えたとうもろこし粉の固がゆですが、現地シェフが作った料理を、まさか日本で食べられるとは思ってもいませんでした。
会場のグランド・エル・サンのクリスタルホールには丸テーブルがフロアいっぱいに並べられ、まずは皆川治市長が開会の挨拶。そして、同市内のワイナリー、グランドエルサンピーノ・コッリーナで収穫されたぶどうを使った白ワインで乾杯し、11皿の料理が1人ずつ次々と運ばれてきます。
これらの料理は、前日の「つるおかふうどフェスタ」でも提供されました(先着順にて、何と無料の大盤振る舞い!)。個別のシェフが作るこれだけの品数を定員の100名分も用意するのは、食材調達からして並大抵のことではなかったはず。日本初の食文化創造都市である「食の理想郷」鶴岡市の行政や食に携わる人々の努力と気合い、心意気を感じずにはいられませんでした。
そして、そんな熱意に応えてか、世界各地から来日したシェフたちは、日本の食文化を学ぶチャンスと考えて、自費で鶴岡にやってきて協力してくれたとのこと。これには本当に驚きました。
創造都市とは、創造性が都市開発の戦略的要素となっている都市であり、ユネスコによってそれらの特定分野がネットワークで結ばれました。いうならば、優れた食文化を持ち、それを尊ぶと認められた都市がつながる世界規模の共同体=仲間ともいうべきでしょうか。会場も始終、和やかな雰囲気に包まれ、何ともうらやましい限りでした。
レセプションのメニュー
マカオのような例外もありますが、食文化創造都市は世界的な観光地ではない場合が多く、現状はまだまだ知られざる美食の地であることがほとんどです。また交通の便が必ずしもいいわけではありません。
ですので、その土地に行かないと食べられない郷土料理を、その土地からシェフがやって来て作ってくれる、しかもこれだけのメンバーがそろうことがいかに貴重な機会だったのか、わかっていただけるかと思います。
そんなレセプションのメニューは、以下のような内容でした。
鶴岡(日本・山形県)


まずは地元の鶴岡より。片岡 忠直シェフと佐藤 渚シェフ(下写真)による「テリーヌ 芋煮 ハモンクルード松ヶ丘 寒椿~庄内の恵みより~」。鶴岡の特産品を使った美しい和風のオードブル。

メリダ(メキシコ)&マカオ(中国)

メキシコのメリダからきたレベッカ・シェフ(下左写真)によるマヤ風「タコのタコス」(左)と、マカオからきた梁 健明シェフ(下右写真)による同地のストリートフード「ポーク・チョップ・バーガー=豬扒包(ツウ・パイ・パオ)」(右)。パポ・セーコというポルトガルのロールパンを使い、その歴史はポルトガル領時代の16世紀にさかのぼるといいます。
前者はとうもろしのトルティーヤの香ばしさとマヤのソースがベストマッチ、また後者はほのかに五香粉の香りがするチャーシュー風豚肉とパンの組み合わせがベストマッチ。マカオらしい料理といえそうです。


ボヒコン(ベナン)

ベナンのボヒコンからきたマリオ・シェフ(下左写真)による「ボミオ」。ブードゥーの伝統的な祭りの際に先祖のために作られていた料理が、現在では家庭料理として親しまれるようになったといいます。ボミオは本来はプリンのようにお椀からひっくり返して提供することが多いようです(下右写真)。
西アフリカ独特のエキゾチックな味わいが期待値大でしたが、鶏肉の出汁が効いていてとてもおいしく食べられました。ボヒコンに行ってみたいです!


サンタ・マリア・デ・フェイラ(ポルトガル)

ポルトガル中部のサンタ・マリア・デ・フェイラからきたエリジオ・シェフ(下写真)による「タラのパストラミ、グアンチャーレと貝のソテー」。第二次大戦中の食料不足から生まれたという、利用可能なすべての食材を活用する料理。豚肉と魚介(干しタラ=バカリャウ)を合わせて作る。炒ったオールスパイスと、コリアンダーの葉の香りが何とも食欲をそそります。

臼杵(日本・大分県)

日本での2番目に認定された食文化創造都市、大分県臼杵市からきた山田 海渡シェフによる「きらすまめし」。残り物の刺身や魚をおろしたあとの中落ちに、豆腐の製造過程で出るおからをまぶしてかさ増しした倹約料理。今ならフードロス削減料理として陽の目が当たることでしょう。

イロイロ・シティ(フィリピン)

フィリピン中部ビサヤ諸島のパナイ島南岸にあるイロイロシティからきたシジ・シェフによる「鮭とバトワンのシニガン(スープ)」。バトワンは現地で採れる酸味のある果実。冷蔵庫がなかった時代から食材を無駄なく一度に使い切れるスープとして伝えられてきました。
カリッと焼いた鮭の食感がスープの酸味とよく合い、私にとっては、今まで食べた中で一番おいしいシニガンでした!

フロリアノポリス(ブラジル)

ブラジル南部のフロリアノポリスからきたナルバル・シェフによる「ムール貝とエビのランベランベ」。ランベランベとは舐めるように食べるといった意味だそうで、魚介の旨味がごはん全体に凝縮されていて、大変美味。パエリアに見た目が少し似ています。

ベルゲン(ノルウェー)

ノルウェーのベルゲンからきたレイモンド・シェフによる「ペルセトースク」(Bergen Pressed Cod)。作り方は鮭の甘塩漬け「グラブラックス」に似ています。クリスマスの時期に食べるベルゲンのもっとも基本的な郷土料理だといいます。北欧らしい濃厚なバターソースがタラによく合います。
市の紋章に干しタラ(バカリャウ、バカラオ)が描かれているベルゲンは、ハンザ同盟都市の時代から北海のタラ漁と干しタラで栄えた不凍港で、かつてのノルウェー王国の首都。
バイキングの航海上の食糧として用いられた干しタラは、中世の頃に、おそらくバスク経由でポルトガルに船上での保存食の知恵とともに伝えられ、大航海時代の屋台骨を支えました。今でもポルトガル料理には干しタラが欠かせません。
つるおかふうどフェスタのふるまいの会場では、ポルトガルのエリジオ・シェフの料理を、日本人シェフとともにレイモンド・シェフがサポートしている姿が見受けられました。
あとで「鶴岡にも”どんがら汁”という伝統的なタラのスープがあり、今回は偉大なタラつながりのイベントでもありましたね」と本人に伝えたら、にっこり笑って、その通りだとおっしゃっていたのが印象的でした。

ニューブランズウィック(米国)

鶴岡市の姉妹都市の米国ニュージャージー州ニューブランズウィックからきたブライアン・シェフによる「赤ワインで煮込んだ牛肉ショートリブのポットパイ」。アメリカらしくボリュームがあり、メリハリの効いた赤ワインのコク味がおいしかったです。

鶴岡(日本・山形県)

ラストは、鶴岡市の宮田 淳シェフによる「ラ・フランスのタルトとつや姫のグラス」。つや姫は庄内米のブランド。地元の果物や乳製品を使った、郷土愛にあふれる、おいしい締めのデザートでした。



食文化創造都市の選定基準
ところで、ユネスコの食文化創造都市=City of Gastronomyのガストロノミーは、食や食文化に関する総合的学問体系を意味します。ですので単に美食の街であれば選定されるわけではないようで、以下のような基準が設けられています。
・都市中心部や地域の特徴である、よく発達した美食。
・数多くの伝統的なレストランやシェフがいる活気ある美食コミュニティ。
・伝統的な料理に使用される地元の食材。
・産業や技術の進歩を経ても生き残ってきた地元のノウハウ、伝統的な料理の慣習や調理方法。
・伝統的な食品市場と伝統的な食品産業。
・美食フェスティバル、賞、コンテスト、その他幅広い対象を対象とした表彰手段を主催する伝統。
・環境の尊重と持続可能な地元製品の推進。
・国民の理解を深め、教育機関で栄養を推進し、料理学校のカリキュラムに生物多様性保全プログラムを組み込む。
特に環境の尊重、持続可能性は特に近年、着目されることが多いですが、今回のレセプションのメニューでも、食材を無駄にしない工夫をなされた料理が多かったのが印象的でした。単なるグルメと違い、一流シェフによるぜいたくな食材を使った料理なら何でも美食とは限らない、ということでしょうか。
なお、今回のレセプションは市民を中心に市内以外にあまりPRはされていなかったようですが、それでも私を含め目ざとい?料理好きが関東などから参加されていました(今後ご興味ある方は、鶴岡市が情報発信するSNSをフォローされることをおすすめします(笑))。
私は世界各地の食文化創造都市を巡ることが最近のライフワークなのですが、どこでも共通しているのは、地元の方々が優しく穏やかで、食を含めた文化的なことに関心を持ち、自分の住む街を愛しておられること。料理は平和の象徴とはよく言ったものです。
もちろん食べもの好きな旅行者にとっても魅力的で、居心地が抜群なのです。鶴岡や臼杵も例外ではなく、またここに戻ってきたいという思いにかられてしまいます。これらの都市は、そもそもツアーバスで物見遊山に押しかけるような有名観光地ではありません。土地の人々とふれあい、その土地にしかない、ありのままの優れた伝統に触れたい旅行者が憧れる目的地だといえると思います。
今回は、歴史ある文化都市であり、恵まれた山海の幸と食を愛する人々の食の理想郷・鶴岡市民の方々と一緒に10周年をお祝いできたことが何よりもうれしかったです。市外からにもかかわらずチケット郵送など快く便宜を図ってくださった市役所の職員の方々にも、心よりお礼を申し上げたいです。
そして食文化創造都市・鶴岡市の次の10年のさらなる発展をお祈りし、引き続きファンとして応援しております。